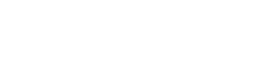便秘になると、腸内に溜まった便で吐き気がしたり
腹部が痛んだりと様々な症状が出ますが、腹部が張ってしまうのも辛い便秘の影響の一つです
便秘により腹部が張ってしまうのは、腸内に溜まっているガスが原因です
これは腸内に蓄積した老廃物から発せられているものになります
長く腸内に留まっている便は、やがて腐敗して体にとって有毒なガスを発生させ始めます
そして、ガスが腸内に溜まっていると善玉菌を減らしてしまい
悪玉菌の比率が上がってしまいます
悪玉菌の割合が増えてしまうと、便秘を解消するどころか悪化させてしまう原因になるので
腸内に溜まっているガスは我慢せずに体の外に出してしまいましょう
ガスが腸内に溜まりやすい人には特徴があります
下半身を圧迫する生活習慣がある人
長時間座っていることが多かったり
締め付けのきつい下着やストッキングを着用していたりする人はガスが溜まりやすいです
何気ない普段の生活習慣かもしれませんが
それによって知らないうちに腸が圧迫されてしまっています
おならを我慢する人
おならが出そうなのに我慢ばかりをしていると、腸に負担がかかります
腸の働きが低下することで、ガスが体の外に排出されにくくなり
結果としてガスが体内に溜まりやすくなります
便秘の人
慢性的に便秘の人は、腸のぜん動運動が起こりにくくなってしまっています
ぜん動運動は便を押し出すだけでなく、ガスを排出する作用も持っているのですが
便秘の人はぜん動運動が起こりにくいため、ガスを排出する力も弱くなりやすくなります

代官山で体質改善 身体の中から綺麗になる頭蓋骨矯正ヘッドスパ
KALEN DAIKANYAMA
小嶺さき
重度の肩こりは、通常の肩こりの症状にプラスして、頭痛やめまい、耳鳴り、便秘、
下痢、微熱、不眠などの症状が起こることもあります。
そのほか、体のだるさや手足のしびれ、疲れがとれにくい、寝つきが悪いといったことも。
このように、重い肩こりは体の他の部分にも不調を引き起こしてしまいます。
デスクワークや長時間運転をする人は同じ姿勢を続けています。そうすると筋肉が疲労して硬くなり、張りやこりを感じる原因となります。
筋肉が疲れて硬くなると、血管が圧迫され、血液が上手く流れなくなります。
これが血行不良となってしまい栄養成分が筋肉に行き渡らなくなってしまいます。
そして痛みを感じる物質が発生する原因ともなるのです。
また、筋肉が硬くなると、末梢神経を傷つける原因ともなります。
末梢神経を傷つけると痛みを感じる物質が発生してしまいます。
この痛みを脳が感知すると、痛みを感じる部分の筋肉を収縮させてしまうのです。
そうすると、更に筋肉が硬くなり、「血行不良」→「末梢神経が傷つく」→「痛み物質が発生」→「痛みを感知」→「筋肉が硬くなる」という悪循環が始まるのです。
肩こりになりにくくするには以下がポイントとなります。
姿勢をよくする
重い物の持ち方に気をつける
体を動かす
体を冷やさない
仕事の環境を見直す
癖を見直す
体に負担が少なく、全身の筋肉をバランスよく使う運動を習慣づけると、
肩こりが起こりにくくなります。
体に負担の少ない運動
ウォーキング
サイクリング
水中ウォーキング
ストレッチ
ラジオ体操
エアコンなどで体を冷やさない。
夏のエアコンによる冷やし過ぎは、特に室内で働いている人が要注意です。羽織るものを用意して、肩や首を冷やし過ぎないようにしたいですね。冬は外の寒さで、筋肉が緊張してしまいますね。上着やカイロなどで、しっかり防寒対策を行いましょう。
仕事の環境を見直すポイント
デスクワークでパソコンを使うという人は要注意です。画面との距離は40cm以上離し、
椅子に座る時には深く腰かけ背筋を伸ばしましょう。
代官山で体質改善 身体の中から綺麗になる頭蓋骨矯正ヘッドスパ
KALEN DAIKANYAMA
竹島育美

イライラと血糖値、PMS(月経前症候群)期間の関係
食事をとると血糖値は上がりますが、急激に上がると反動で
今度は血糖値が下がりすぎることがあります
その時にイライラや空腹感が起こりやすくなります
女性ホルモンの関係で、生理前は血糖値は上がりやすい状態になっています
血糖値は緩やかに上げて緩やかに下げるのが、イライラを減らしやすくなります
飲み物を甘くないものに
液体と固体だと液体の方が急激に血糖値を上げやすいため、低血糖を起こしやすくなります
生理前はジュースやコーヒー、紅茶に砂糖をたっぷり入れるのは避けるのがおすすめになります
なるべくお水や炭酸水、お茶で乗り切りましょう
おやつも砂糖や小麦・米が一番はじめに来ないもの
お菓子のパッケージには原材料表示がしてありますが、この順番は重量順です
チョコやクッキーは、原材料をみると砂糖や小麦が一番はじめにくるものが多く
おせんべいやポテトチップスは米やじゃがいもが一番はじめになります
これらは血糖値を急激に上げやすいです
チョコレートならカカオマスが砂糖より多く含まれるもの
クッキーなら、大豆やおからが一番はじめに来るものがおすすめです
間食を食べるなら、ナッツ類もおすすめになります
甘い朝ごはんは注意
朝ごはんにドーナッツや菓子パンを食べると血糖値が上がりやすくなります
特に前日の夕食から時間が空いているので、朝ごはんの影響は強くなりやすくなります
パン派の方はライ麦パンや全粒粉パンに切り替えて
チーズトーストなどにしてみてはいかがでしょうか
ごはん派は卵かけごはんや、納豆ごはんが手軽でおすすめになります
血糖値を上げにくい食物繊維が取れるスープや味噌汁
サラダや漬物をプラスするのもおすすめになります

代官山で体質改善 身体の中から綺麗になる頭蓋骨矯正ヘッドスパ
KALEN DAIKANYAMA
小嶺さき
生理前は浅い眠りになりやすい
良い眠りを得るには、内臓などの深部体温の低下が不可欠になります
しかし、生理前は、高温期で体温が高い状態であるため
寝る前に眠りに適した体温まで下がりにくくなります
その結果、眠り自体が浅くなりやすくなります
眠りが浅いと、朝の寝起きも悪いことが多く
日中のイライラや憂鬱感なども自然に増えることが考えられます
対策は、まずは深部体温を下げること
そして、特に寝る前の自律神経を整えることになります
よい眠りができれば、深い睡眠時に体の修復が行われ
なんとなくだるいといったプチ不調を和らげやすくなります
生理前はなるべく湯舟に浸かる
お風呂は体を温められる上、自律神経の副交感神経を優位にしやすくなります
また、生理前は体温が下がりにくくなっています
お風呂で体温を少し上げることで、自律神経の働きでより体温低下を促すため
熟睡に導いてくれます
40度のお湯に、15分~20分を目安に浸かりましょう
夕方に運動をする
体温や血圧が高い夕方に運動を行いましょう
お風呂と同様に、事前に体温を上げておくことが、寝る前の体温低下に繋がりやすくなります
エスカレーターを使わず階段を利用する
1駅分歩く、トイレでスクワットする、など簡単な運動をしましょう
寝る前に目や耳を温める
一日中PCやスマホを見ていたり、いろいろな音を聞いて24
時間ずっと稼働しっぱなしの目と耳を、電子レンジで温めたタオルで温めてみましょう
血管が拡張して血液循環がよくなり
筋肉がほぐれて疲れが徐々に緩和しやすくなります
子宮卵巣を温める
電子レンジで温められる、柔らかい湯たんぽを
子宮卵巣の上においてお休みしましょう
血流がアップすると、細胞の新陳代謝や老廃物の排出が促進されます
ただし一晩中温かい電気毛布やホッカイロを使用するのは眠りを浅くしたり
低温やけどの可能性があるので避けてください
寝る前にうっとりすること
寝る前はスマホを見たり、考え事をしたりと
交感神経が優位になりやすくなります
ゆったりとした深呼吸や、気持ちの良いストレッチをすることで
副交感神経が高まりやすくなると
血圧や深部体温が適切に下がり、よい眠りができるようになります

代官山で体質改善 身体の中から綺麗になる頭蓋骨矯正ヘッドスパ
KALEN DAIKANYAMA
小嶺さき
冷え性には手足などが冷えていなくても、内臓が冷えている隠れ冷え性の場合があります。
このような隠れ冷え性は、内臓型冷え性といわれ手足などは冷えていないのに、お腹が冷たくなっています。
内臓型冷え性は冬よりも夏に悪化することが多いのも特徴です。
夏は暑さによる熱が逃げやすい身体になっているため、冷房で直接肌を冷やされると余計に熱が逃げやすくなってしまいます。
内臓型冷え性について
手が暖かいと冷えはあまり気にならないので内臓型冷え性の症状が重くなっている…
ということも少なくありません。
内蔵が冷えてしまうと、下痢や便秘を繰り返したり胃腸の調子が良くなかったり
といった症状になってしまいます。
内蔵が冷えてしまうと、内蔵の機能が低下し免疫機能も低下してしまう為、善玉菌などの活動が妨げられ下痢や便秘を引き起こしてしまうんです。
体全体の免疫力の低下(免疫力が30%程度低下するといわれています)により、風邪をひきやすくなったり、アレルギーが起きやすくなります。
内臓型冷え性を改善する方法
内臓型冷え性の場合、まず体幹を保温することが大切です。
腹巻や靴下を履いて、お腹とくに下半身の熱を逃さないようにすることが必要です。
へそから1、2cm下のところにカイロを貼ってお腹を温めるのも効果的です。
また、寝ている間は身体が冷えやすいので、できるだけ暖かい格好をして寝るようにしましょう。
ただし、厚着をして汗をかいてしまわないように。汗で身体が冷えてしまっては逆効果です。
内臓冷え性に効く食事
根菜類や大豆食品、スパイスなどの身体を温める食品を積極的に取ることに加えて、食事は冷たいものだけではなく、お味噌汁など常に1品以上は温かいものを取り入れるようにしましょう。
冷たい物は避けましょう。サラダは温野菜に、ジュースは氷を入れないようにするなどの心がけも大切です。
食べる時は良く噛むのも消化を促せるので胃腸の負担が減り、内臓型冷え性に効果があります。

代官山で体質改善 身体の中から綺麗になる頭蓋骨矯正ヘッドスパ
KALEN DAIKANYAMA
竹島育美